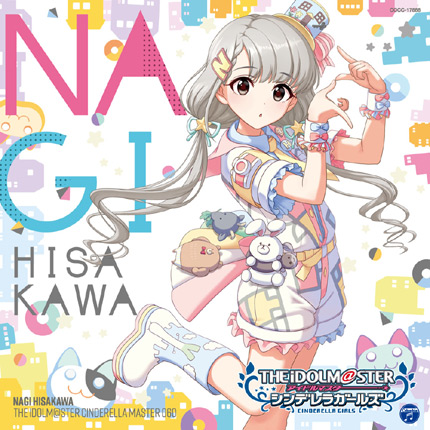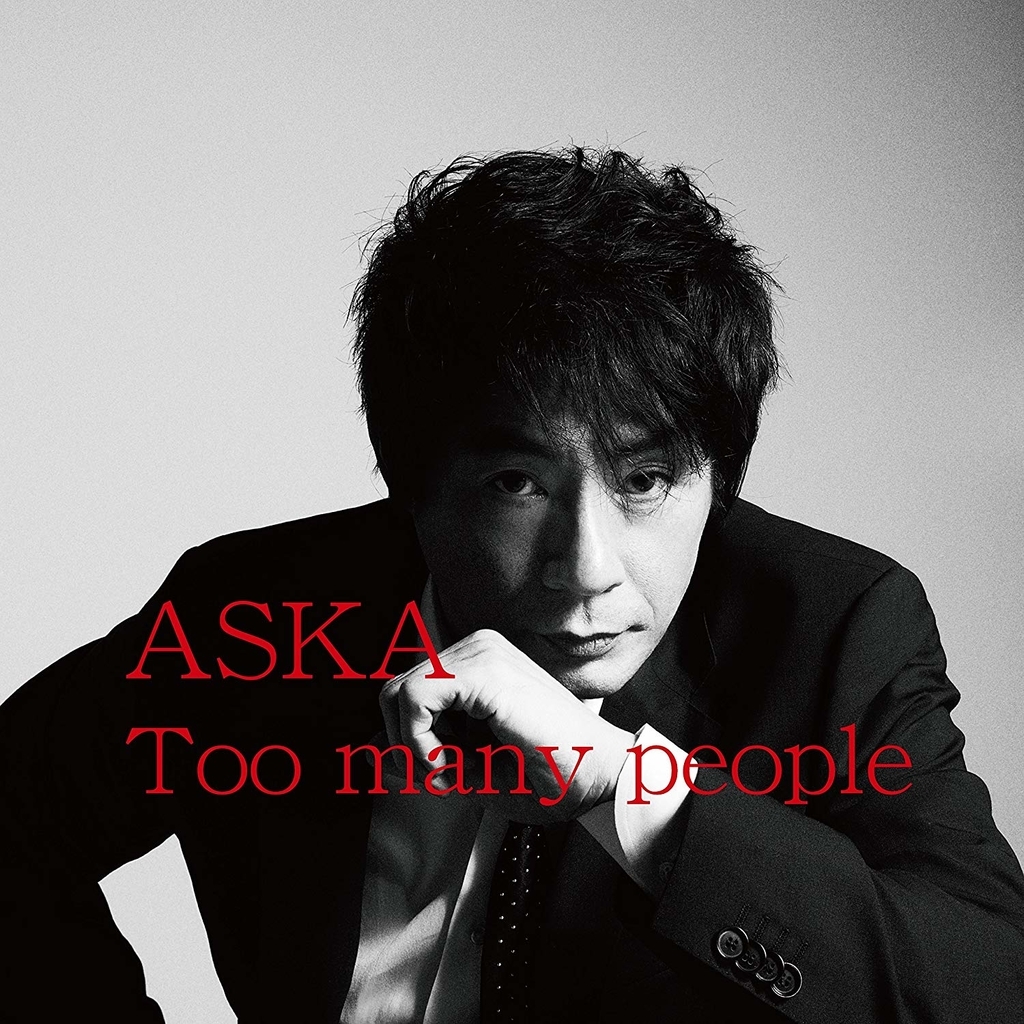はじめに
「焼畑農業」を誤用した言説が巷に溢れている。
そのような言説は、主に2種類に大別できる。
一つは、焼畑農業を環境破壊的な農法だと誤解した上で、焼畑農業の是非についてや、森林火災など他の環境問題に絡めて論じる言説。
もう一つは、焼畑農業そのものを論じるのではなく、「○○は焼畑農業のように人材を使い潰している」「次から次へと業界を荒らし回る○○は焼畑的だ」など、別の物事について論じる際に、ネガティブな意味合いを含んだ比喩として使用する言説である。
この記事では、様々な言説が飛び交うTwitterを中心に見ていくことで、焼畑農業に関する誤解を解きほぐしながら、主に後者の言説(誤解に基づいた比喩として焼畑農業を使用する言説)を類型化して分析し、ひいてはそのような誤用が生じる要因について地理学的な観点から探ってみたい。

目次
- はじめに
- 誤解される焼畑農業
- Twitterの「焼畑」誤用言説の類型化
- 「焼畑」誤用が生じる要因
- 要因Ⅰ: 公的機関・マスメディアを介したネガティブな世論の形成
- 要因Ⅱ: 学校における地理教育の影響
- 小括: 「焼く」という言葉の強さ
- おわりに
- 参考文献